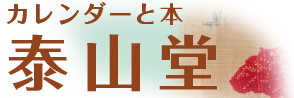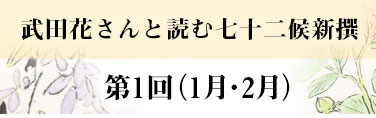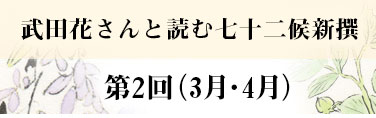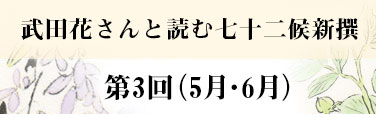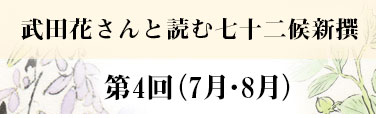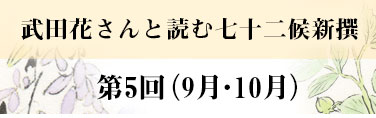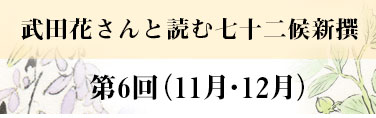武田花さんと読む七十二候新撰
武田花さんと読む七十二候新撰 -1月・2月-
七十二候新撰を藩主水戸斉昭に献じた佐藤成裕は、江戸後期の著名な本草学者です。本草学は、漢方薬の原料となる動植物や鉱物を採集して研究し、医療に利用する学問でした。当時の学問は中国の古典を学ぶことが基本なので、成裕ももちろん漢文の素養がありました。随筆『中陵漫録』に、「余薩州に在りて、某に学びて漸く大学一巻を暗読す」とあります。成裕は19歳の若さで薩摩藩に招聘され薩州での採集をおこなっていますが、同時に勉強もしていたようです。
同じく『中陵漫録』に誤字考と題する一節があります。「余、幼より好く書を写して、人是を見て誤字多しと云。こヽに於いて、諸の字書を集めて参考するに、似て非なるもの多し。蠶は平声にして蚕は上声也。蠶の略字にあらず。すなわち寒蚓の名也。蟲と虫と義を同して、虫は音毀也。蟲の略字にあらず。蛇の類の名なり。」七十二候新撰の六月にも「桑入蠶室」がありますが、虫と蟲が別字というのは本当のようです。ミミズ(寒蚓)を原料とする漢方薬の別名として「堅蚕」があり、蠶はカイコですが蚕はミミズでヘビ類?になるのでしょうか。ちなみに成裕は、長崎で中国人から中国語の発音を習っており平声、上声などの知識もありました。
このように漢文に深く通じていた成裕ですが、誤字と思われるものもあります。十月の「茱萸染紅」の2文字目は、伝写本では「莄」になっていますが「萸」に改めました。ただし、これは白井光太郎が誤写した可能性もあるので、もし水戸彰考館に原本が残っているのであれば確認したいところです。
前置きが長くなりましたが、このたび写真家・エッセイストの武田花さんと、七十二候新撰の読み下しと意訳に挑戦します。花さんのお父様は小説家の武田泰淳、お母様は随筆家の武田百合子です。武田泰淳は、中国文学や中国と深い関わりのある作家でもあります。花さんは、写真家として野良猫のモノクロ写真で有名ですが、最近は「目玉が入れ替わってしまって」カラー写真を撮っているとのことです。無理強いのお願いに快く応じて頂きました。
花さんが持ってきたのは、昭和40年版の上田萬年ほか編『大字典』、大正6年の初版より版を重ねている文字通り大字典です。字典を引き引き、まず一月・二月から始めます。二人とも専門外のこと故、間違いもあるかと思いますが、ご容赦の程お願い申し上げます。
(文責:熊谷 泰)

武田花さんと読む七十二候新撰 -3月・4月-
15候の「木筆空に画く」ですが、『牧野富太郎植物記5 木の花』(あかね書房,1974年初版)の「モクレンとハクモクレン」の項に次の文章があります。
「モクレンのつぼみは、その形が筆の頭のようにみえるので木筆(もくひつ)という漢名もありますが、中国人はモクレンのつぼみの形にたいそう興味をもっているようです。「木筆空(くう)に書す」などということばも見られます。つまりモクレンの筆のような形のつぼみが、ゆらゆらゆれて空に字を書いているようだという意味でしょう。」
この本は牧野富太郎の名を冠していますが、執筆しているのは牧野の40余年来の弟子であった微生物学者の中村浩で、牧野の教えを書き留めた「植物ノート」を元にしているようです。「木筆空に書す」も牧野のことばのように思われます。本稿では、畫=画から「木筆空に畫く」と読み、字ではなく絵を画いていると想像してみました。
17候の「雉鳴き翅を撲つ」は春分の候です。春になるとオスのキジは縄張り行動で、ケンケーンと大きな声で鳴き、胸を張って両方の羽をハタハタと大きな音をたてて打ちます。これをキジのホロ(母衣)打ちと呼ぶようです。母衣は、「鎧の背につけて流れ矢を防ぎ、また存在を示す標識にした幅の広い布」(大辞泉)で、キジの羽ばたく様子がホロに似ているからと言われています。一方、キジの鳴き声を古くはホロ、ホロロと聞きなしたようなので別の説もあるかもしれません。「けんもほろろ」という言葉も、キジの鳴き声と言われています。昔、実家の雑木林の裏にキジを飼っている家があり、その鳴き声が驚くほどやかましく突っ慳貪だったことを思い出しました。
18候の「碧桃競い發く」の碧桃には惑わされました。最初は桃の花なので桃色に彩色しましたが、碧桃という言葉から白い花ではないかと思い直し、白花で彩色しました。しかし碧桃の碧は色を表しているのではないようです。現代中国で「碧桃」は桃の変種で、日本でいうハナモモを指します。一般的には八重の桃色の花です。古代中国では桃は神聖な植物だったので碧は神聖の意味の美称でしょうか。「七十二候新撰」の碧桃は一重のように見えます。
(文責:熊谷 泰)

武田花さんと読む七十二候新撰 -5月・6月-
26候の「杜鵑啼血す」、杜鵑はホトトギスです。子規、時鳥、不如帰など多くの漢名がありますが、正岡子規は、結核で喀血する自分をホトトギスになぞらえて子規を俳号としました。ホトトギスが「啼いて血を吐く」と言われるのは口の中が赤いためです。大きく口を開いて啼(鳴)くので目立つのでしょう。杜鵑や不如帰という漢名は、古代中国で蜀の望帝、杜宇に関する伝説に由来します。「杜宇は不品行により帝位を逐われホトトギスに化して「不如帰」と鳴きながら飛び去ったという」(菅原浩、柿澤亮三編著『図説 鳥名の由来辞典』、柏書房)ホトトギスという和名も鳴き声を聞きなしたもので、その特徴のある強い鳴き声はいろいろな聞きなしや説話を生んでいます。私が子供の頃の聞きなしは「特許許可局」でした。
松尾芭蕉は24歳の寛文7年(1667)に次の句を詠んでいます。(『続山井』)
岩躑躅(いわつつじ)染(そむ)る泪(なみだ)やほとヽき朱(ほととぎす)
「岩躑躅の花を染めているのはホトトギスの赤い涙」
岩躑躅を自生のヤマツツジとするなら赤い花を開くのは4月から6月、ホトトギスは夏鳥として5月に渡来するので、この句を実景とするなら5月か6月でしょうか。、最後の一字を「朱」としているのが面白い。ここでもホトトギスは赤と結びついています。岩躑躅は、昔の着物で表に出る絹地が紅、裏側の絹地が紫の重ね色目の名前でもあるので、その連想から芭蕉は染めるという言葉を使ったのかもしれません。
31候の「躑躅大に照らす」と33候の「杜鵑花盛んなり」には、躑躅(ツツジ)と杜鵑花(サツキ)が出てきます。漢名の杜鵑花は、中国でホトトギスが鳴く頃にツツジが咲くから名付けられたようです。しかし中国では冬鳥で、春の終わりから初夏に日本や北の方に飛び去るので、日本とは別の印象のように思います。杜鵑花は現代中国でツツジ科の漢名になっており、様々の栽培品種に、烈香杜鵑・奪目杜鵑・肉色杜鵑・牛皮杜鵑・睫毛杜鵑など面白い名前が付いています。一方、躑躅も漢名ですが、これは中国語では「さまよいうろうろする」意味で、トウレンゲツツジに羊躑躅という名前が付いています。ツツジには有毒な種類もあり、羊がこれを食べると中毒して躑躅(ふらふら)して倒れることから名付けられたそうです。
(嶋田英誠編『跡見群芳譜』http://www.atomigunpofu.jp/)
サツキは日本固有種で本来漢名はありません。日本では、サツキが他のツツジ類より1ヶ月ほど遅く開花することからツツジとサツキを区別しますが、植物分類からは大きな違いはありません。江戸時代にはツツジやサツキの栽培品種の開発がさかんにおこなわれ、園芸が武家や庶民に大流行しました。江戸染井の植木屋、霧島屋伊兵衛(伊藤伊兵衛)が元禄5年(1692)に著した『錦繍枕(きんしゅうまくら)』には、ツツジとサツキそれぞれ160種以上が花の絵とともに目録になっています。
31候のツツジは、花弁の形や雄しべの数からモチツツジを思いながら薄紅紫色に彩色しました。33候のサツキは自生のサツキを思い紅色に彩色しましたが、雄しべの数が多すぎるようです。
(文責:熊谷 泰)

武田花さんと読む七十二候新撰 -7月・8月-
37候の「孑孑化蚊」、「孑孑」は正しくは「孑孒」で、蚊の幼虫であるボウフラを意味する漢語(中国語)です。どちらの文字も中国で「子」から派生した文字で、「孑」は右の腕がないこと、「孒」は左の腕がないことを意味します。(大修館書店『新漢語林』第二版, 2011)昔は水溜まりや池、水槽でボウフラは身近なものでした。その独特の屈曲運動からボウフリムシ、ボウフリと名付けられ、大槻文彦が明治二十四年に刊行した『言海』には次のようにあります。
ぼうふりむし 棒振蟲 夏、蚊ノ卵ノ、溜水ノ中ニテカヘレルモノ、形、小釘ノ如クニシテ、尾ノ末ニ岐アリ、身ニ細キ毛アリ、静ナルトキハ、水面ニ浮ビ、驚クトキハ沈ム、其泳グトキ、體ヲ屈折スルコト、棒ヲ振ルガゴトシ、小米粒ノ形ヲナシ、又化シテ蚊トナリテ飛ブ。略シテボウフリ、訛シテボウフラ。孑孑
簡潔にしてボウフラの動きを印象的に描写したなかなかの名文だと思います。ところで最後に「孑孑」とあるのが気になります。前述のように、ボウフラの中国語は現代でも「孑孒」で、「孑孑」は孤立や孤独な状態を示す言葉でボウフラの意味はありません。啓成社より大正十三年に刊行された『大字典』には、「孑」字のみ収録されており「孒」字はありません。「孑」字の項に、「孑孑と重ねボウフリ蟲の義とす。之れ其蟲が孑の字に似たるによるか。」とあります。白井光太郎が明治二十四年に水戸彰考館で伝写した文字も、明らかに「孑孑」と重ね文字です。恐らく佐藤成裕のオリジナルの『七十二候新撰』でも同じ文字だったでしょう。日本では江戸・明治・大正と誤ってボウフラに「孑孑」の字を当てていたように思われます。
『言海』や『大字典』を見ると、明治・大正頃のボウフラの一般的な呼称はボウフリムシやボウフリだったように思われますが、棒振りとはどんな動きでどんな職業の人がする動作なのでしょうか。天秤棒をかついで急ぎ足で歩くとボウフリムシのような動きになるのでしょうか。人間の所作は記録に残らないので自分で試してみるしかなさそうです。ボウフラは七十二候の題材としてちょっと珍しいものですが、緑色の蚊帳の匂いとともに夏の候としてふさわしいものと思います。
44候の「芙蓉晩醉」、フヨウが晩になって酔うとは何かと思いますが、これはスイフヨウ(醉芙蓉)という八重咲きの品種のことのようです。(『七十二候新撰』の絵ではあまり八重咲きに見えませんが)フヨウは中国原産ですが古くから品種開発がおこなわれており、清朝初期の1688年に刊行された園芸書『花鏡』に既に醉芙蓉が紹介されています。スイフヨウは、『牧野新日本植物図鑑』によれば、「花の色は朝咲きはじめた時は白色、午後にうすもも色、夜にかけて紅色に変り、翌朝になっても落下しない。したがってこの木には紅、白、うすもも色の三色の花がまじって着き大変美しい」とあります。中国では、一日に3回色が変わることから「三醉花」とも呼ばれるそうです。八月下旬から九月初めに各地で咲くようなので一度は見てみたい花です。
(文責:熊谷泰)

武田花さんと読む七十二候新撰 -9月・10月-
九月、十月になると七十二候の題材も急に秋めいて、花はハギとキクだけで、虫や鳥、実が増えてきました。
佐藤成裕(中陵)は、宝暦12年(1762)江戸青山に生まれ、17歳頃から関東諸州を採薬のために遊歴し、20歳にして薩摩藩から産物調査のため招聘されています。その後、備中松山藩・米沢藩(上杉鷹山)・会津藩など日本各地で産物の採集や本草学の講義をおこないました。39歳(1800)の時、水戸藩6代藩主徳川治保(文公)に召され水戸藩士となり、87歳で亡くなるまで50年近く水戸で暮らしました。『七十二候新撰』を9代藩主徳川斉昭(烈公)に献じた天保14年(1843)には、既に82歳でした。
成裕は、各地の山野を渉猟して植物や鳥獣を採集・捕獲しました。また自ら庭に植物を植え、鳥は飼育して本草の研究をおこないました。なかでも鳥は特に好きだったようで、文化5年(1808)の序がある鳥類の分類と飼育法をまとめた『飼籠鳥(かいこどり)』20巻を著しています。『七十二候新撰』にも10種の鳥が描かれています。
秋分初候(53候)の「鶺鴒翩翩」は、ハクセキレイです。『飼籠鳥』巻15の鶺鴒の項には、和名としてトツギヲシエドリ、イモセドリなどが挙げられた後、信州ではイシタタキ、播州方言としてカハラスズメ、関東方言としてセキレイ、江戸方言としてハクセキレイが記されています。セキレイは漢名の読みで都会の知識人の言葉なので、庶民はその尾を叩く姿からイシタタキと呼んでいたと思います。また「諸州共に秋早く来る。三月の頃より深山に移る」とあります。ハクセキレイは、1970年代頃までは北海道や東北地方で繁殖し、秋に関東にやってくる冬鳥でしたが、近年は関東でも繁殖する留鳥になっています。また、他のセキレイ類であるセグロセキレイやキセキレイと同様に水辺でよく見られ、尾を上下に振るさまと、波を描くようにスイスイと軽やかに「翩翩」と飛ぶ姿が印象的です。現在は水戸市の鳥にも選ばれています。ハクセキレイは人をあまり恐れず都市化にも順応性が高いため、近年生息範囲を広げています。
秋分次候(54候)の「鶴過暗夜」ですが、暗い夜のツルの渡りのようです。野生のツルは、現代では北海道のタンチョウ、鹿児島のマナヅル・ナベヅルなど限られた場所でしか見られません。しかし、江戸時代には日本全国で普通に見られる鳥で、武家の鷹狩りに使われ、食用にも供されました。『飼籠鳥』巻18の鶴部には、サギやコウノトリ類なども含んで27種の鳥が挙げられていますが、ツル類は灰鶴(和名タヅ、古名マナツル)、白鶴(和名丹頂、トウツル)、黒鶴(和名ナヘツル、キヌカツキ)など10種です。灰鶴(マナヅル)の項には、「何國にても秋彼岸の比(ころ)に盛(さかん)に至る」とあります。白鶴(タンチョウ)の項には、「諸州共に秋彼岸の比より渡り来る。しかれと此丹頂はその中に在ることなし。此種は朝鮮の地方に多し。此地に至ては秋群れ来る中に希(まれ)に是れありと云」とあり、マナヅルは日本各地に渡ってくる、タンチョウは朝鮮には渡るが日本には来ないと記されています。但し、タンチョウは「官家(かんけ)籠中(こちゅう)に養(やしな)ひ或(あるい)は庭池(にわいけ)の間に貯(たくわ)ふ」とあり、公的に飼育されていたとあります。
『飼籠鳥』は、佐藤成裕が水戸藩に仕えて8年後に刊行されたと思われますが、時代を下って『七十二候新撰』が烈公に献上される前年、水戸に偕楽園が造園されました。偕楽園開園当時の絵図には、千波湖西側の田圃にツルが描かれています。これらのツルは、その姿からタンチョウ・ナベヅル・ソデグロヅルと考えられていますが、残っている文献からも餌付けされていたようです。偕楽園のツルは、佐藤成裕にも身近なものだったと思われます。
さて「鶴過暗夜」で夜の渡りをするツルはどのツルでしょうか?彩色はマナヅルを想定しておこないましたが、水戸彰考館に残っていると思われる『七十二候新撰』の原本を見てみたいものです。
(文責:熊谷泰)

武田花さんと読む七十二候新撰 -11月・12月-
霜降末候(61候)の「柿分黄紅」は、柿の実が黄色に、葉が紅色に分かれる様を詠んだものと考えました。カキノキは、新しい小さな葉の明るい新緑が、大きくなると深く暗い緑色に変わる変化や、秋が深まり鮮やかな紅色に紅葉する様子など、とても色を楽しめる樹木です。子供の頃、カキノキの若葉と同じ色をしたイラガに刺された時の鋭い痛みが忘れられません。
立冬次候(63候)の「蝙蝠作声」。「七十二候新撰」の題字は、原著者である佐藤成裕の深い漢文の素養に基づいています。何か中国に典拠があるようにも思われますがよくわかりません。コウモリの鳴き声は、大方が人間の聞き取れない超音波らしいので、「作声」はどんな声なのでしょうか。コウモリは、今では想像しにくいですが大変縁起のよい動物で、江戸時代には着物の文様によく用いられました。元来は中国において、「蝙」=「変」、「蝠」=「福」の同音から、「福に変わる」縁起のよいものと考えられました。中華料理店に「福」の字が逆さまに飾ってあるのを見かけますが、これも「倒」=「到」の同音から、「福が到る」を意味します。江戸時代の日本では語呂合わせが大好きでしたが、中国も同じようです。
小雪次候(66候)の「賓雁送語」。「賓雁」の賓は、客人(まろうど)のことで、中国では毎年秋に北から渡来して春に帰って行く雁(マガン)を客人、あるいは客人の手紙を持ってくる使いとも見立てました。佐藤成裕の『飼籠鳥』巻16の雁の項には、漢名の別名として「羽書使者」も挙げられています。
小雪末候(67候)の「蝦苗上市」。佐藤成裕が長く仕えた水戸藩の霞ヶ浦北浦ではテナガエビ(川エビ)漁が盛んです。現代でも全国漁獲量の50%を超え、夏に生まれたエビを秋以降に獲り、地元では「ザザエビ」と呼ばれるそうです。(https://www.ibaraki-shokusai.net/season/fish/ebi/)
大雪末候(70候)の「南天映燭」ですが、ナンテンの漢名のひとつに「南天燭」があります。南天の赤い実を灯火(ともしび)に見立てたようです。
最後に立冬初候(62候)の「楸莢猶懸」に戻ります。「楸莢」は楸(キササゲ)の莢(さや)の意味です。1885年(明治18年)刊行の大槻文彦の言海には「ひさぎ」の項に次のようにあります。なお、「きささげ」の項を見ると、木角豆(キササゲ)ノ義、楸(ひさぎ)に同じとあります。
ひさぎ(名)楸[久シキニ耐ユル木ノ意カト云]樹、直ニ聳エ、上ニ枝ヲ分ツ、枝、葉、共ニ対生シ、新出ノ茎葉ハ、共ニ黒クシテ、長ジテ緑トナル、葉ハ、桐ニ似テ、五尖ニシテ、鋸歯ナシ、太サ六七寸ヨリ尺ニ至ル、夏、尺許ノ穂ヲ出シテ花ヲ開ク、胡麻ノ花ノ如クニシテ、浅黄ニ紫點アリ、莢ヲ結ブ、長サ尺餘、垂ル事、十六ささげノ如シ、故ニ、木ささげノ名モアリ、莢、春ニ至リ、自ラ裂ケテ、子、風ニ飛ブ。
「七十二候新撰」で描かれた絵を見る限り、「楸莢」はキササゲのさやであることに間違いはありません。キササゲの実(さやとその中の実)は現在でも漢方薬として使われており、昔は民間薬として身近に植えられていました。おそらく佐藤成裕の家の庭にもあったでしょう。1875年(明治8年)に生まれた詩人の蒲原有明が、晩年1947年の回顧自伝小説「夢は呼び交す-黙子覚書-」の中で次のように回想しています。
「あれには本当に困ったなあ。ほら、あの日除になるといって、青桐代りにうえさせたきささげだよ。土用時分になると、毎年忘れずに、向いの家からその実を貰いに来たものだ。老人がいて、寝たり起きたりしている。薬にするからだといってたね。」
「そうですとも。うちでは入用がありませんから、いくらあげても好かったのでございます。ちっとも惜しくはなかったのですが、梯子を掛けたり、屋根に上ったりして、高い枝から実を取って遣るのでしょう。一仕事でございましたよ。」(中略)
「それにまた実を取らないでそのまま附けて置くと、冬になってからあの莢がはじけて、古綿のようなこまかいものが飛び出して来ましたね。そこらじゅうを埃だらけにします。それを掃除するのが骨折でございました。」
蒲原が戦前に住んでいたのは鎌倉あたりのようです。キササゲの実(梓実)が民間薬として知られていたことがよくわかるエピソードです。
現在は東京近辺でキササゲをあまり見かけませんが、秋田や青森など東北地方へ行くとよく目にします。キササゲの特徴は、集まって垂れ下がるインゲン豆を長くしたような1尺(約30cm)ばかりの莢(さや)と、蒲原が日除けにしようとした桐の葉のような大きな葉です。
「七十二候新撰」の読み下しと意訳をお願いした写真家・エッセイストの武田花さんが撮ったキササゲの写真があります。花さん得意の白黒写真ですが、キササゲの特徴が余すところなく捉えられています。聞けば、東北旅行の青森で、風にひるがえる大きな葉に心を惹かれて撮影されたとのことですが、家内の実家のある秋田の夏を思い起こさせる大好きな写真です。
(文責:熊谷泰)

武田花『道端に光線』(中央公論新社)より